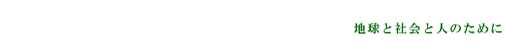| 受験生への学科長メッセージ『国際公共政策学科で学ぶこと』 | |
学科長:松野 明久 教授
国際公共政策学科では、法学・政治学・経済学の基礎を学び、日本を含む現代国際社会が抱える諸問題の解決に貢献する理論や政策について探求します。もちろん国際的に活躍するためには、高度な英語のコミュニケーション能力も身につける必要があります。
なくならない戦争や紛争、貧困や格差、増え続ける難民、深刻化する気候変動、頻発する災害、脅威となる感染症等は、どれも国際社会が一致協力して取り組まなければならない問題です。そのために高度な知識・スキルを身につけ、しっかりした見識をもち、異なる背景の人たちと一緒に何かを作り上げていく力をもった人材が求められており、国際公共政策学科はまさにそうした人材の育成を目指しています。
国際社会における「公共」とは何でしょうか。国際社会は統一された政府もないし、警察も裁判所もありません。各国には主権があり、国際社会はよく「アナーキーな」社会だと言われます。一方で、みんなが共通に問題だと思うことはあり、異なる言語、文化、宗教を背景とする人びとが一緒になって原則やルールを作っています。そのようにしてグローバル・ガバナンスが徐々に形成されてきました。国際社会ではいろいろな価値がぶつかり合うことになり、重要なことは人を説得する力なのですが、それは強引に相手をねじ伏せる力でも、議論で打ち負かす力でもなく、普遍性をもった論理を提示することのできる英知です。「公共」とは英知でなければなりません。
また、国際「公共」といっても私たちの日々の暮らしと関係のない遠いところで議論されているものではありません。国際連合は2015年からSDGs(エス・ディー・ジーズ:持続可能な開発目標)を掲げ、人間、地球及び繁栄のための行動計画を推進しています。それは2030年までに貧困、不平等、気候、環境破壊、繁栄、平和、正義などについて17個の目標を達成するという壮大な計画です。その計画は「この共同の旅路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓う」と謳っています。「公共」とは誰一人取り残すことなく、持続可能な繁栄を作り上げることなのです。そしてその目標は日本においても達成されなければなりません。
みなさんもこの地球社会の大胆な変革をめざす壮大な「共同の旅路」に参加してみませんか。