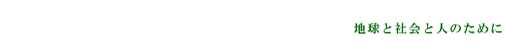| 専門教育科目詳細 | |
入門概説系
| 民法入門 | 選択必修 | 1年次 |
| 民法は私法の一般法であり、私法分野の法律を学ぶ上での基本として必修すべきものである。民法典は、総則、物権、債権、親族および相続の5つの編で構成されているが、本講義では、民法学の基本的な考え方を習得させることを目的とし、民法の歴史、民法の基本原理(所有権絶対の原則、契約自由の原則、過失責任主義の原則、家族法における個人の尊厳と両性の本質的平等)、民法による社会秩序の形成・維持(権利濫用の禁止、信義誠実の原則、公序良俗)などにつき講述する。実際の裁判例を読み、民法の意味につき自ら考える訓練も行う。 | ||
| 憲法入門 | 選択必修 | 1年次 |
| 近代憲法の基本原理を確認した上で、「日本国憲法」の基本的事項を解説する。その際、法学科において憲法についての詳細かつ網羅的な講義が開設されていることを前提として、その時々のトピックスに関連する問題や話題性のある判例を中心に、わが国の憲法をめぐる重要な論点についての鳥瞰図を示す。それを通じて、憲法に係る基本的重要事項についての基礎的知識を授けるとともに、発展的な学習の契機を提供する。 | ||
| 国際関係論入門 | 選択必修 | 1年次 |
| 国際関係論をこれから学ぼうとする者に、国際関係論がどのように現代世界の政治状況を理解し説明しようとしているのか、基本となる概念と見方を提示する入門コースである。本講義では、1.現実主義、2.リベラリル制度主義、3.社会構成主義、4.意思決定論を中心に概観しながら、具体的な国際政治の事象を例をとりあげて考える。 | ||
| ミクロ経済入門 | 必修 | 1年次 |
| 経済学の初歩的な考え方を習得する。将来どのような分野に進むにしても必要となる、社会政策や社会現象を考察する力を育てる。講義は以下の内容で進める。1.資源分配と市場メカニズム、2.需要と供給 3.限界分析と需要曲線、4.限界分析と供給曲線、5.市場均衡と比較静学、6.関連トピックス、7.厚生経済学と政府介入の効果、8.市場の失敗、9.不完全競争の分析、10.不確実性の経済学・ゲーム理論 | ||
| マクロ経済入門 | 選択必修 | 1年次 |
| マクロ経済学では、経済生活の重要な指標となる所得、物価、雇用といった、国民経済における集計的経済変数がどのように決まるのか、また、その短期的変動である景気循環や長期的趨勢である経済成長がどのようなメカニズムで動くのかを明らかにする。この入門的講義では、このような分析を行うために必要なマクロ経済モデルの基本的フレームワークを考察する。また、そのモデルを用いて、長期成長の源泉は何か、国際的所得格差の源泉は何か、および日本の不況の源泉は何か、など、いくつかの現代的問題に対する議論の整理を試みる。 | ||
| 国際公共政策 | 必修 | 1年次 |
| この講義の目的は、現代の国際社会が直面している、いくつかの重要な公共政策課題を入門的に取り上げ、今後の学習への関心を高め、専門分野へと進む動機付けを行うことにある。その例として、冷戦終結後の政治秩序、各種の地域紛争、国連を中心とした国際安全保障構造、人間の安全保障、環境と開発、貧困削減、国際通貨体制、国際貿易システム、非政府部門、などが考察される。 | ||
| 政策データ分析入門 | 選択必修 | 2年次 |
| 政策分析に必要となる基本的な統計の知識を身につける。まず、統計分析の有効性を説明した後、いくつかの確率分布と基本統計量などを学ぶ。同時に、それらを使用して問題の分析にあたった具体例を紹介する。次に、社会調査の方法として、調査対象の選び方やアンケートの配布の仕方を身に付ける。その後、標本抽出、推定と検定、 最小二乗法など、より高度な分析技法に移る。また、中級レベルの講義に進むために必要な数学も訓練する。 | ||