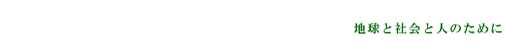| 専門教育科目詳細 | |
政治学系
| 日本政治思想史 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 幕末から昭和戦後期までの政治思想を概説する。講義の主な内容は、1.「開国」による儒教の華夷秩序の崩壊から近代西欧の国際秩序への編入、2.明治維新と近代国家の形成、3.日清日露戦争と帝国主義への参入、4.大正デモクラシーから昭和期のマルクス主義へ、5.総力戦と戦中期のリベラリズム、 6.象徴天皇制と戦後憲法秩序の形成、7.55年体制の形成から冷戦の終焉まで。 | ||
| ヨーロッパ政治史 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 19、20世紀のヨーロッパ政治史を、ドイツを中心にしながらもヨーロッパ諸国の相互影響関係、全ヨーロッパ的な時代コンテクストを押さえながら講義する。近代ナショナリズムの成立と国民国家の形成、国家論・国家思想、帝国主義とナショナリズムの変容、第一次大戦と戦間期ヨーロッパの状況、大衆民主主義と議会制デモクラシーの危機、ファシズムと反ファシズム、過去の克服とヨーロッパへの道などが主な内容となる。 | ||
| アジア政治史 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 20世紀前半期の中国政治史について講義する。講義の対象となる時期の中国は、中華帝国が解体して軍閥政治から国民党の政治へと展開し1949年には中華人民共和国が成立する。本講では、当該時期の中国政治の軌跡を、(1)「中国」という政治空間の構造と特質(通時的視角)、(2)20世紀前半期の国際政治とりわけアジア諸地域との相互連関性(共時的視角)、ならびに(3)東アジアの新環境における日中関係(今日的課題)に留意しながら概観し、あわせて従来の中国近代政治史像を再検討したい。 | ||
| 外交政策論 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 本講義では日本とアメリカ合衆国を例に外交政策を論じる。歴史的事実を踏まえながら、日米両国が、国際環境の変化の中でどのような対外政策を行ってきたのかを分析し、現代における対外政策の理解を深める。米国独立革命から米英戦争、南北戦争、両世界大戦迄を概観した上で、冷戦期とポスト冷戦期のアメリカ外交に焦点をあてる。一方、日本については開国以後の対外関係を概観し、特に第二次世界大戦での敗戦、国際社会復帰、対米関係、中国やソ連との外交関係、ポスト冷戦期の国際情勢の変化等について、各時代の政策決定者がいかに対応したのかを考える。 | ||
| 安全保障政策論 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 国家安全保障、勢力均衡、集団安全保障、地域紛争など、安全保障論の諸概念を理解した上で、国家は安全をいかに確保するのか、国際紛争をどのように予防し解決するのか、地域紛争の予防と解決にはどのような手段が必要かという問題を論じる。国際紛争の原因や解決に関する理論、政策策定・実施・評価をとりあげ、日本を例に、国際情勢・地域情勢の分析や、戦略目標の策定、対応能力の整備、同盟管理などを考察する。後半では、地域紛争の発生から解決まで諸要因を分析し、国連、地域機構、政府、市民社会がどのように関与したかに焦点をあて、具体的事例を論じる。 | ||
| 平和学 | 選択必修 | 3,4年次 |
| この授業は、主として核兵器と平和の関係に、歴史的な視点と理論的な観点から焦点をあてる。国際社会に対して最も大きな影響力をもつ核兵器保有国であり実際に核兵器を使用した唯一の国であるアメリカは、どのような核戦略や核兵器政策を展開してきたのか。また、核兵器が国際平和に対してはたしてきた役割は何であったのか。これらの問題の考察を行なう。そしてそのような考察を通じて、平和とは何か、平和を達成し維持するためには何が必要なのか、というより大きな問題に対するてがかりを受講生に提供する。 | ||
| 現代ヨーロッパ政治 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 欧州の政治過程および政治文化を概観することにより、欧州の動向を、静的な政治構造の次元にとどまらず、歴史的ダイナミズムのなかで理解することを目指す。前半では、欧州統合の歴史と現状、社会民主主義・グリーン・右翼ポピュリズムなどの政治諸潮流、移民・民族問題など、全欧州的なテーマを取り上げ、欧州に関する内在的理解を深めてゆく。後半では、日本としばしば対比されるドイツ政治の特質について、隣国との和解、地域統合への関与、覇権国家への態度などの論点に即しながら講述する。 | ||
| 国際行動論 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 行為主体の行動を分析する方法を学ぶのが基本目的である。具体的には、ゲームの理論や国際公共財の基本的な概念を学び、その基礎知識を活用して、「合理的」な行動を各行為主体がとると仮定した場合に起こる問題を提示し、その「解決」に向けた方向性を探って行く。例えば、各主権国家が「協調」行動をとりやすくするためには、どんな環境条件が必要かなどを考えていく。最終的には、具体的な政策課題を題材に、分析を試みる。ミクロ経済学などの基礎知識が役に立つ。また、簡単な四則計算程度の数学を用いる。 | ||
| 国際機構論 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 国際社会の「組織化」は今日の国際関係の大きな特徴の一つといえる。本科目は、国際社会の「組織化」の動きを支える機構的な側面と多国間外交について考察する。具体的には最も普遍的な政府間国際機構である国連システムや、より地域的な政府間国際機構における法と政治と公共政策形成プロセスを検討する。国益と国際公共利益とのバランス、国境を超える市民社会や政策ネットワークの拡大、さらに、国際機構における日本の多国間外交のあり方などについても議論する。 | ||