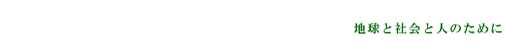| 専門教育科目詳細 | |
経済政策系
| ミクロ経済学 | 選択必修 | 2年次 |
| ミクロ経済学の基礎理論を講義する。特に資源配分メカニズムの中で最も代表的な価格メカニズムに焦点をあて、市場での価格を通じた資源配分の機能に関する理解を深めることを目標とする。具体的には、1.消費者・選好、2.企業・技術、3.競争均衡とその効率性、4.公共性と外部性、などのトピックについての講義を行う。 | ||
| マクロ経済学 | 選択必修 | 2年次 |
| ここでは、初級のマクロ経済入門の次の段階として、標準的な中級マクロ経済学を講義する。授業目的は,マクロ経済分析で使用されるさまざまなモデルの構造を正しく理解し,実際の経済政策分析に適切に応用できるようになることである。概ね、以下の内容を講義する:1.経済活動水準の測定、2.GDPの決定メカニズム、3.家計消費、4.投資、5.貨幣需要と貨幣供給、6.経済成長の理論、7.不完全雇用経済、8.マクロ安定化政策、9.公債と財政赤字。 | ||
| ゲーム理論 | 選択必修 | 2年次 |
| 意思決定者の間で戦略的な利害の対立がある状況の分析ツールであるゲーム理論の基礎を概観する。ゲーム理論の基本的な解概念であるナッシュ均衡およびその思考体系の理解を目標とする。抽象的な議論のみならず、より具体的な応用例も交えて講義を行う。トピックとしては、1.静学ゲーム:ナッシュ均衡、2.動学ゲーム:サブゲーム完全均衡、3.不完備情報ゲーム、などをカバーする。 | ||
| 政策データ分析 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 政策データ分析で修得した統計分析技法の応用と中級レベルのデータ分析技術を身に付けることを目的とする。政治動向、法と経済、政策評価などに関する具体的な問題をとりあげ、必要データを入手し分析をおこない、結果が意味することを議論する。一方、社会調査において一般的に使用される多変量解析の技法を説明する。特に、多重回帰分析においては多重共線性、不均一分散、不偏推定量など計量経済学で使用する基本的概念を説明する。さらに、行列と行列式に関する中級レベルの理解を目的とする。 | ||
| 国際経済政策 | 選択必修 | 3,4年次 |
| これまでの経済政策は、効率性の観点からあるいは市場の失敗を是正する観点から議論されてきた。ところが実際的な経済政策を考えるとき、これだけでは不十分だと考えられる。輸入制限が国全体としていかに大きな負担を強いられるかがわかっていても、実際にはそのような政策が実施される。したがって実際の経済政策を論じるには、政策決定の政治過程を考慮することが必要不可欠であると考える。国際経済政策では、多国間での金融財政政策の協調、国際通貨制度、地域間の貿易協定・貿易政策においてどのような政策決定がなされているか、理論的かつ実証的に検討する。 | ||
| 国際貿易と投資 | 選択必修 | 3,4年次 |
| この講義では国際貿易および投資の現実をよく理解していく上で必要となる基本的な知識や理論を紹介する。次のようなトピックスについて講義する。技術水準の差と貿易構造、要素供給の差と貿易構造、規模の経済性と貿易、不完全競争と貿易、貿易政策の手段、関税政策、非関税障壁、戦略的貿易政策、WTOと地域貿易協定。 | ||
| 国際金融と開発 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 標準的な国際マクロ経済学の入門コースとして、国際金融論の基礎を学習する。国際経済システムは、技術進歩と経済成長を通じてますますその相互依存関係を緊密化させている。ここでは、相互依存緊密化のダイナミズムを明らかにするとともに、それによって生じる国内および国際政策課題にどう取り組むかを考察する。国民所得と国際収支、為替レートとマクロ経済調整過程、国際通貨制度、国際マクロ政策協調、国際資本市場の発展、発展途上国と国際資本市場などのテーマを扱う。 | ||
| 経済発展 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 経済発展は金銭的のみならず質的にもより高い生活水準を支える基本条件であり、全ての国家、とりわけ発展途上国にとって主要な目標であると言える。本講義では、開発経済学の理論や実証研究をもとに、日欧米など先進諸国や近年のアジア諸国の経済発展の過程を分析し、また発展途上国が現在直面している特有の問題をテーマごとに体系的に学習する。さらに、多国間貿易協定や国際環境条約などグローバル化に伴う外的制約にも着目しながら21世紀の経済発展の展望について考察する。 | ||
| 公共経済学 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 公共政策を客観的に分析・評価するための標準的な手法を習得することを目的とする。これから政策研究の世界に入ろうとする学生のための入門講義とする。社会システムにおける政府部門、市場、制度の役割についての基礎的な考え方の枠組みを提供するとともに、現代日本の主要な公共政策課題である税・年金制度、医療福祉制度、雇用制度や、グローバルな公共政策課題である途上国開発援助、環境などのテーマについて理論的、実証的な側面から考察を行う。 | ||
| ヒューマン・キャピタル | 選択必修 | 3,4年次 |
| 経済学または人事管理論でなされている人材に関する議論を紹介し、経済社会における教育・訓練の役割を検討する。経済学の視点からとり上げるトピックは、教育と経済成長、技能と生産性、教育と所得分配などである。人事管理の視点からとり上げるトピックは、配置と育成、企業内訓練、昇進管理、学歴と賃金などである。また、企業の訓練制度や国の教育制度に関する国際比較も行い、それらの違いが経済的競争力のみならず人間開発を通じた社会資本の蓄積水準にどのように反映されるのかも議論する。 | ||