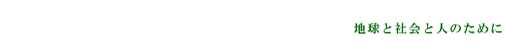| 専門教育科目詳細 | |
法学系
| 国際法1 | 選択必修 | 3,4年次 |
| この講義は、国際社会における法である国際法の基本的な知識を講義することを目的とする。国際法1は、国際法学の体系の前半部分を取扱う。内容は次のものを含む。国際法の概念(国際法の意義と特徴など)、国際法の法源(条約、慣習国際法など)、国際法と国内法、国際法の主体、国家(国家の概念、国家承認、政府承認、国家承継など)、国家領域(国家領域の性質、領域の得喪など)。なお、国際法1~3は連続した講義であり、それをすべて受講することによって国際法全体を体系的に理解することができる。 | ||
| 国際法2 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 国際法1に引き続き、国際法の基本的な知識を講義する。内容は次のものを含む。海洋法(領水、公海、大陸棚、排他的経済水域、深海底など)、空の国際法(領空、宇宙空間など)、特殊な地域(南極の地位など)、国際機構(国連その他の国際機構の活動原則など)、個人と国際法(外国人の法的地位、犯罪人引渡し、難民、人権の国際的保障など)、外交関係法(外交関係、領事関係など)。 | ||
| 国際法3 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 国際法2に引き続き、国際法の基本的な知識を講義する。内容は次のものを含む。条約法(条約の効力や留保など)、国家責任(国家責任の要件と効果など)、国際紛争の解決(国際裁判その他の解決方法など)、国際安全保障(戦争の違法化と安全保障など)、国際人道法(武力紛争時に適用される規則など)。 | ||
| 国際取引法 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 国際取引においては、実務と理論のいずれを欠いても、有利な取引を組み立て、紛争を解決することはできない。この講義は、国際取引の制度面とこれを支える国際慣習および法的ルールを機能的に理解し、国際取引法の基本的な考え方と国際的に通用する高度な法的思考力および説得力の養成に努める。それを達成するために、国際取引に関する日本の裁判所の判例を分析し、議論することとし、さらに関係する契約書、法令および文献でこれを補足する。 | ||
| 国際環境法 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 環境保全をめぐる国際的な法的枠組みについて概説的な講義を行なう。その際、予防原則や原因者負担原則等の環境法の一般原則に留意しながら、「気候変動に関する国際連合枠組条約」や「生物の多様性に関する条約」などの国際条約及びそれを具体化する国内法をめぐる諸問題を法解釈学的観点から検討する。なお、二酸化炭素の排出権取引など経済学などの関連する学問領域と連携を要する諸問題について、本学科の特性を活かして、積極的な連携を図る予定である。 | ||
| 国際人権法 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 人権の保障は、国内法(主として憲法の人権保障規定)を通じてなされるのが原則である。しかし、第2次大戦後の国際社会では、人権を国際的に保障するための様々な活動が展開されており、それが一国の法と実行に影響を及ぼすこともある。そして、このような国際社会の活動の中から、いわゆる「国際人権法」と称される一群の法規範が出現している。この講義は、「国際人権法」の基礎的な知識と考え方を習得することを目的とするものである。国際法1~3の応用科目である。 | ||
| 特別講義(現代家族の法と政策) | 選択必修 | 3,4年次 |
| 高齢・少子化、国際化、情報社会化、男女共同参画化が進むなかで、現代の家族生活は著しく変化しつつある。婚姻法・離婚法の変容、人工授精・体外受精など生殖革命と親子法の改革、未成年者の保護、養子制度、成年後見制度、相続と遺言法など検討すべき問題は多い。本講義では、これら現代の家族法上の法理論的・法政策的な諸課題について現状を分析し、将来の方向を探る。また外国の家族法・政策との比較研究を行うとともに、国際的な人的移動に伴う家族の形成・維持・解消に関連して生じてくる法律問題について講述する。 | ||