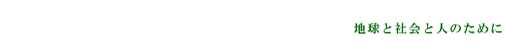| 専門教育科目詳細 | |
応用展開系
| インターンシップ | 選択必修 | 3,4年次 |
| 受講者は、インターンシップを通じて実務上のスキルや実践的な統計処理技法などを学ぶことができ、社会人・組織人としての疑似体験ができる。まずクラスで過去にインターンシップを経験した先輩たちから体験を聞き、これを参考にインターンシップ受け入れ先を探す。受入先でインターンシップを始める前に次のような点について授業で発表する。1)習得したい経験と仕事の仕組や組織運営等調べたいテーマ、2)それをどこまで、どのように明らかにするかという計画、3)受入先と仕事の内容に関する準備調査、など。実際のインターンシップは、教員との連絡のもとに、授業とのもとに、授業と重ならないように基本的に休業期間中に行うことが多い。修了後、報告会で体験を報告する。 | ||
| ネゴシエーション | 選択必修 | 3,4年次 |
| 他の国家あるいは他人との関係を成立させること、また、そこから生じる紛争を処理することは、人と人の交渉すなわちネゴシエーションである。この講義では、プロフェッショナルとしての高い交渉能力を身につけたネゴシエーションに強い人材の育成を目的としている。講義では、まず、交渉の場面を映像で紹介した後、交渉のためのプランニング、ネゴシエーション実技、交渉の事後処理の重要性等を学ぶ。その後、対話論、原則立脚型交渉論、ゲーム理論、静かなリーダーシップ、反省的実践家などの理論について学びながら、交渉事例のプロセスを分析し諸理論の有効性を検証する。最後に法的紛争や国家間交渉の模擬交渉を設定し、実際に交渉を経験する。 | ||
| 人間の安全保障 | 選択必修 | 3,4年次 |
| 「人間の安全保障」をテーマにとりあげ、同概念が登場した政治的、学問的背景を考察したのちに、国際機関や各国政府などが同概念をどのように位置付けているのか概観する。そのうえで、日本の国際政策にとっての「人間の安全保障」の意味と、今後の方向性について考える。授業は、安全保障概念の拡散とその背景、人間の安全保障-概念的考察、国際機関の政策と人間の安全保障 などのテーマから構成される。 | ||
| 特別講義(NPO) | 選択必修 | 3,4年次 |
| NPO、NGO、ボランティアなど、民間非営利セクターに関する最新の研究動向を講義と文献講読を通じて学ぶ。特に、NPOがなぜ存在するか、営利組織や行政機関と本質的にどこが違うか、世界的にその役割が注目されるようになったのはなぜか、NPOは寄付やボランティアをどのように活用しているか、NPOのマネジメントはどうなっているか、NPOの法制や税制はどうなっており、どのように改革されるべきか、といった論点を検討していく。 | ||
| 特別講義(地域統合) | 選択必修 | 3,4年次 |
| この講義では、財・サービス、資本のモビリティの高まりが各国・地域の相互依存関係、とりわけ産業構造にどのような影響を与えるのかを理論面および実証面で明らかにする。貿易自由化や地域貿易協定、多国籍企業行動の活発化がグローバルな産業地図をどのように塗り替えているのかを考察する。これらの全体を見るためには価格と数量の調整を明示的に考慮した一般均衡的枠組みが有効である。 | ||
| 特別講義(環境と開発) | 選択必修 | 3,4年次 |
| 環境と経済開発は相互補完的な側面と競合的な側面の両方を持っている。本講義では、開発経済学、環境経済学などをもとに環境と経済開発の問題を分析する。政策評価においては、経済的効率性だけでなく環境や生活水準の持続性など多様な評価基準を用い、また理論的、実証的手法を組み合わせて、社会的により望ましい公共政策を模索する。主なテーマとして、所有権と天然資源管理、経済成長と環境基準、国際貿易と環境、また地球温暖化と国際的制度設計など環境保護と開発に関する現代の諸問題を取り上げる。 | ||
| 特別講義(社会科学方法論) | 選択必修 | 3,4年次 |
| 経済学や政治学はその隣接関連分野と総称して社会科学と呼ばれる。いずれも現実の「社会現象」を探求する学問である。しかし、現代経済学の特徴は、数学モデルと経済変数間の統計的解析にある。これは歴史学や、伝統的な政治学、社会学と著しく異なった方法である。同じ社会を対象としながら、このような違いはどうして生じるのか。その妥当性と限界はどこにあるのか。そして、そもそも経済学と政治学等の他の社会科学を共に学ぶことによって意味ある社会の全体像を描くことができるのか。本講義ではこのような問いに答えることを内容とする。 | ||
| 特別講義(地域経済社会論) | 選択必修 | 3,4年次 |
| フランスを中心としたヨーロッパ諸国の経済・社会・文化について、国際政策との関係において統計的に分析するとともに、関連する文献を批判的に分析することで、クリティカル・シンキングのトレーニングを行う。統計的な分析の方法を身につけることを目的とするとともに、単に知識を記憶するのではなく、課題探求能力、独創的創造性、論理的思考力などの、大学審議会答申によって今後の日本の大学教育における課題とされている新しい能力の開発のためのさまざまな試みも行う。 | ||
| 特別講義(シティズンシップ論) | 選択必修 | 3,4年次 |
| 人々は特定の政治共同体の成員となることを通じて、一定の権利と義務を獲得する。そのような権利・義務をシティズンシップといい、近代の政治共同体では人々は市民的、政治的、社会的という三つのシティズンシップを獲得するとされている。しかし、実際には、政治共同体のあり方はそれぞれ国によって異なり、また、ジェンダー、エスニシティ、高齢化、グローバル化などの問題によっても変容を迫られている。この講義では、そのような政治共同体のもとで、シティズンシップをいかにとらえるべきかを考察する。 | ||